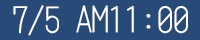いしにかこまれたくうかん、トバリシティ。この街は険しい山を切り崩して作られたため、街の中でも所々高低差がある。そんな街に、達はやって来ていた。
自転車をトバリシティの入り口のゲートにある駐輪場に止めていると、ジラーチが背中越しに小さく潜めた声でへと話し掛ける。
「ここが、トバリシティ?」
「そうだよ。どこから行こうかなあ。……ジラーチはどこに行きたい?」
こんな昼時の明るい時間、それも人が多い場所でジラーチを連れて歩くのは初めてのことだ。ボールから出たドンカラスと並んで歩きながら、はカジノやデパート、それにジムなどを思い浮かべてジラーチへと小声で尋ねる。
トバリシティへと来る前に予めトバリシティのことを聞いていたジラーチは、少し考え込んだ後に「デパートがいいなあ」と言った。
「デパートだね。いいよ、行こうか」
それに快く頷くと、達はデパートへと向かった。
トバリデパートは街の中心にあり、すぐに着いた。人がたくさんいるからか、ジラーチは落ち着き無く辺りを見回す。
「、。人がいっぱいいるよ」
「緊張する?」
「少しだけ……」
小声で大丈夫だよ、とジラーチを安心させるように告げてから、入り口の自動ドアを抜ける。夏の昼間は暑く、デパートの中に入った途端に感じる少しひんやりとした空気が気持ち良い。デパートの中は外よりも賑わっていた。どうやらみんな夏の陽射しの暑さから、この涼しいデパートへと逃げているようだ。
デパートは地下一階から五階まであるが、先ずは地下から見て回ろうと決めてエスカレーターに向かった。エスカレーターを初めて見たジラーチは、エスカレーターに乗っただけではしゃいだ声を上げる。そうしてエスカレーターで下りた地下は食品売り場とフードコートがあり、昼間のこの時間は昼食をとる客で賑わっていた。
「これだけ人がいると、リュックから出ても目立たないかもしれないね。たくさんの人が色々なポケモンを連れているし」
この前のような怪しい人間もいないだろうと思ったのだ。それにこんなに人目がある所では、いくら最小限に声を抑えてるとは言えど、いちいちリュックの方へと振り返って会話をする方が怪しく見えそうだ。ドンカラスも確かに、と頷く。するとの言葉を聞いたジラーチは、するりとリュックから抜け出しての腕の中に収まった。
「えへへ。やったあ!」
を見上げて笑顔を浮かべると、ジラーチは辺りのものの全てを、物珍しそうに眺めた。
それからある一点で眼を止めると、指を指す。
「。あの、あれ、食べたいな」
ジラーチが食べたいと言ったのは、ポケモン用のお菓子であるポフィンだった。どうやら出来立てのようで、甘くて香ばしい香りが売り場から漂ってくる。
「いいよ。好きな味を選んでね」
ポフィン売り場に向かうと、ジラーチはポフィンの匂いを確かめるように大きく息を吸い込んだ。
「あまくて、いい匂い!」
うっとりとした顔でジラーチはの腕の中から抜け出すと、甘い味のポフィンを手に取った。はそれを受け取ると、カゴの中に入れる。
「ドンカラスは、渋い味で良いよね?」
ポフィンの匂いを確かめるようにすんすんと鼻を鳴らしていたドンカラスに尋ねると、ドンカラスは頷く。それから甘い味は甘い味でも、材料となった木の実が違うポフィンに、同じく渋い味でも材料となった木の実が違う渋い味のポフィンをいくつかカゴに入れた。
レジに向かう途中で「様々な地方の名産コーナー」なるものに立ち寄ると、ホウエン地方の名物だというフエン煎餅に、ジョウト地方の名物だといういかり饅頭などもカゴに入れて会計を済ませる。そしてその後、フードコートで軽い昼食にした。
「おなかいっぱい!」
「そうだね。私もお腹いっぱいだな」
ジラーチはの片手に抱かれながら、ぽんと自分のお腹を叩く。それを見てドンカラスが笑い、釣られても笑ってしまった。
そうして他愛も無い話をしながら三人は下の階から順番に見て回り、五階までやって来ると、五階にある「憩いの広場」のベンチに腰を下ろした。憩いの広場に来る頃にはお昼も過ぎて午後の二時を回っていたので、人は疎らにいるだけだ。ジラーチは辺りの様子を伺ってから、の腕の中からふわりと浮かび上がると、の隣に腰を下ろした。
「、つかれてない?」
「うーん。ずっと歩いたり立ったりしていたから、少しだけ疲れたかな」
「大丈夫?」
「うん。少し休めば大丈夫だよ」
疎らにいる他の客に聞こえないように、小さく潜めて会話をする。それからは徐に立ち上がると、ベンチに荷物を置いてすぐ傍の自販機に向かった。その後を、ジラーチとドンカラスがついていく。
「ジュースでも飲もうか。どれが良い?」
ドンカラスはサイコソーダを翼で指し示したが、ジラーチは自販機のディスプレイを眉間に皺を寄せて眺めている。どうやら悩んでいるらしい。
ジラーチが悩んでいる間にがサイコソーダのボタンを押すと、がしゃん、と音が響く。出てきたサイコソーダの口を開けてドンカラスの口元に缶を近づけると、ドンカラスは大きく口を開けた。零れないように注意を払いながらドンカラスの口にサイコソーダを流し込むと、ドンカラスは喉を鳴らして一気に飲み干す。
それでもまだジラーチは悩んでいて、が缶を捨てる頃に、漸く「よし」と意気込み、ミックスオレのボタンを押したのだった。
「わあ、甘くておいしい」
「気に入った?」
「うん!」
ベンチに座り、先程買った渋い味のポフィンを袋から取り出しながら、はジラーチの顔を見つめた。甘いミックスオレがとても気に入ったのか、ジラーチはとてもゆっくりと飲んでいる。
「デパートはどう?」
「いろいろあって、見たことないものばかりで、すっごく楽しい!」
「喜んでくれて良かった」
ドンカラスにポフィンを差し出すと、ドンカラスは嘴でポフィンを啄ばんだ。ドンカラスが二つ目のポフィンを食べ終える頃にはジラーチもミックスオレを飲み干していて、今は甘いポフィンを両手で持って齧っている。
「ミックスオレも、ポフィンも、おいしいねえ」
ジラーチがあんまり嬉しそうにするので、はジラーチの頭を優しく撫でた。ジラーチはえへへ、と笑いながら眼を細める。寝ちゃ駄目だよ、とが笑うと、ジラーチは寝ないよ、と慌てて眼を開いた。ドンカラスが可笑しそうに喉を鳴らして笑っている。
そうして憩いの広場でゆっくりと休み、デパートを出る頃には午後三時を回っていた。